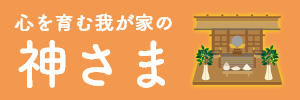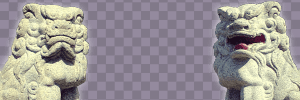-
赤倉神社

- 御祭神
-
大山津見神
- 鎮座地
-
七尾市三引町53-5、9
- 氏子区域
- 七尾市三引町
- 由緒
- 赤倉神社は田鶴浜町三引に在り。大山津見神を祀る。相伝う。推古帝の時の鎮座に係れりと。又、社伝に據るに聖武天皇天平2年春東宮眼を患ひ給い医薬効なし偶々母后夢に老翁あり。翁告げて謂う能州赤蔵山の大権現に祈らば即ち癒えんと、覚めて之を帝に奏す。帝由りて中納言藤原諸末を下して祈らしめ給う、是時多武峯定恵の高弟愚渕法師は30余僧を率いて隨い来り権に一宇を建て檀を設けて法華会を始めけるに靈験立どころに現れ、東宮忽ち癒え給う是に於て諸末命を承けて材を鳩め工を集めて神殿を営構し赤蔵山広運五里の地を社領となし、愚渕止りて祀事を修む。後白河帝の時神殿再興して三引村の山林田畝方一里を寄進し社僧120坊を置き給い赤蔵山上一本宮寺と称し、一時石動山天平寺と相駢いて勢威四方を圧せしかど天正年中社殿仏堂悉く兵燹に罹れりと。後長連頼鹿島半郡を領しける時宮殿僧坊を再興し寛文元年6月寺社領田61石6年を寄進し以て長氏の祈願所と為せり、奥院本社、拝殿神明堂、白山堂、講堂、鐘堂、天神堂、二王門、辻堂、地蔵堂寺及び栄春院怡岩院、千手院赤蔵坊寺は皆比時を以て就り規模の雄大なること郡中に冠たり。後年漸く衰敗して、今復田寺昔の視なしと品も今存するところの本殿拝殿等は実に当時長氏の造営に係れるものにして今猶多く仏像等を蔵す。又、末社に菅原神社あり亀山天神と称し寛文の初め長連頼再建したりしを明治28年火に由りて明年京都北野神社の分霊を勧請せり、其の後明治41年4月9日石川県の許可を得て同字鎮座の末社白山社、神明社、愛岩社、波仁屋社と共に当神社に合し其の祭神を併せ祀る。
- 宮司
-
岡本 尚士(伊夜比咩神社 宮司)
- TEL
本務神社
兼務神社
-

嶽神社
七尾市能登島鰀目町31-6
-

白比古神社
七尾市白浜町21-1
-

大宮神社
七尾市能登島野崎町48-52
-

柴山神社
七尾市能登島閨町63-27
-

柴山神社
七尾市能登島無関町オ22乙
-

柴山神社
七尾市能登島半浦町17-46
-

別所神社
七尾市能登島別所町54-2
-

日吉神社
七尾市能登島八ケ崎町9-35
-

多賀神社
七尾市能登島二穴町イ56
-

日吉神社
七尾市能登島日出ケ島町ヨ29
-

八幡神社
七尾市能登島通町ノ2
-

柴山神社
七尾市能登島南町ハ-42
-

春日神社
七尾市能登島長崎町32-12甲
-

先﨑神社
七尾市能登島須曽町23-29
-

白山神社
七尾市能登島祖母ケ浦町4-51
-

佐波神社
七尾市能登島佐波町ヲ27
-

大宮神社
七尾市能登島曲町9-32乙
-

久木神社
七尾市能登島久木町7-20-2
-

大津八幡神社
七尾市大津町ナ50
-

火宮神社
七尾市杉森町ワ32
-