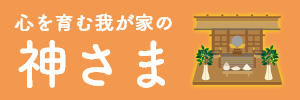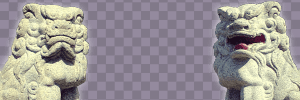-
波自加彌神社

- 御祭神
-
波自加彌神 正八幡神
- 鎮座地
-
金沢市花園八幡町ハ165
- 氏子区域
- 金沢市花園八幡町二日市町白山市野地町
- 由緒
金沢市二日市町・花園八幡町入会地に鎮座し、波自加彌神(はじかみのかみ)、一国一社護国正八幡神を主神とし、相殿に神明、春日、諏訪、薬師の神々を配祀する。旧社格は郷社で、延喜式内の古社である。創建は 718(養老2年)で、始め四坊高坂の黄金清水(こがねしょうず)に鎮座していたが、寿永年間の源平合戦の砌、兵火のため社殿亡失し、現在地の田鹿(たぢか)八幡宮に遷座され、復合の神社となったが、正四位上の神階をもつ波自加彌神が八幡神より上位と考えて、社名が今のものに変更された。
田鹿八幡宮にとっては、庇を貸して母屋を取られたことになる。波自加彌神は、調味医薬・五穀豊穣の神として全国に類例のない食産神(しょくさんしん)で、歯でかんで辛(から)いもの即ち、生姜(しょうが)・山椒(さんしょう)・山葵(わさび)などの古語で『薑(はじかみ)』を語源とする。境内には、神功皇后の三韓征伐の折、朝鮮半島より医薬としての生姜を我が国に初めて伝えた、朝臣武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)を祀る摂社諶屏堂(せっしゃじんべいどう)が鎮座し、生姜の古名を名乗る本社との関係が伺える。古くはこの地方一帯が生姜の栽培地であったので、守護神として波自加彌神を祀ったことが起源とされるが、田近郷(たぢかごう)の総社として、その地名が田近、田鹿、波自加彌と転語したとの説もある。社前を流れる河原市用水は、1686(貞享3年)に完成したが、建設した中橋久左衛門は、本社の神託によって現れた白狐の足跡をヒントに用水路とした。以来用水の守護神としても仰がれてきた。平成13年(2001年)、1300年の式年大祭を迎えた。- 宮司
-
田近 章嗣
- TEL
-
各神社では神職が外祭等により不在する場合があります。
又、祈祷を受ける場合予約が必要な場合もあります。 - FAX
076-258-0703
- URL
兼務神社
-

八幡神社
白山市柳原町ヘ93-1
-

白山別宮神社
白山市別宮町ロ84-1
-

八幡神社
白山市別宮出町ハ14
-
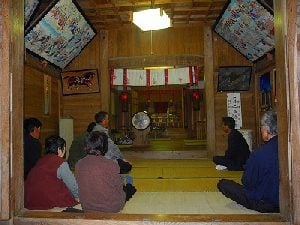
八幡神社
白山市渡津町ロ155乙
-

笥笠中宮神社
白山市中宮ヘ1
-

八幡神社
白山市上野町イ62-2
-

八幡神社
白山市出合町イ224
-

八幡神社
白山市出合町ト169
-

八幡神社
白山市五十谷町イ144
-

佐野神社
白山市河内町福岡張1
-
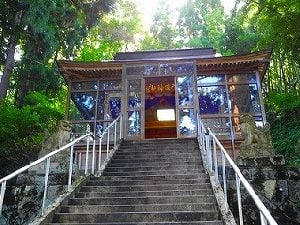
八坂神社
白山市河内町江津己17
-

八幡神社
白山市河内町吉岡ヘ111
-

少彦名神社
河北郡津幡町浅谷ト72
-

八幡神社
金沢市鞁筒町イ130
-

八幡神社
金沢市薬師町ハ135
-

川崎神社
金沢市北森本町ル46
-

水分神社
金沢市福畠町チ63
-

軻遇突知神社
金沢市不動寺町ト10
-

熊野神社
金沢市俵原町2-90
-

菅原神社
金沢市梅田町チ62
-
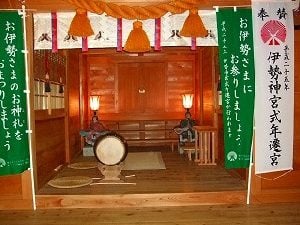
八幡神社
金沢市塚崎町ホ195
-

忠縄神社
金沢市忠縄町89
-

熊野社
金沢市竹又町イ138
-

神代神社
金沢市地代町イ31
-

八幡神社
金沢市浅丘町ニ1
-

貴船神社
金沢市千杉町チ70
-

山王神社
金沢市深谷町ホ110
-

日吉神社
金沢市深谷町ヲ9-乙
-

小野白山神社
金沢市小野町ロ102
-

八幡神社
金沢市四坊高坂町ロ40
-

四王神社
金沢市四王寺町イ123
-

譽田別神社
金沢市堅田町ト151
-

花園神社
金沢市月影町イ62
-

日吉神社
金沢市桐山町ヨ13
-

御馬神社
金沢市久安1丁目178
-

岩出神社
金沢市岩出町ホ116
-

八幡社
金沢市岸川町ヲ129
-

横川日吉神社
金沢市横川1丁目74
-

横川神社
金沢市横川4丁目1
-

八幡神社
金沢市榎尾町ソ7-3
-