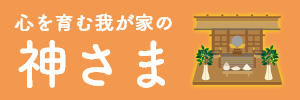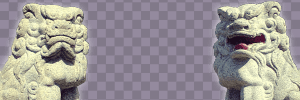- ちょっと教えてください
- 石川県特有または全国的に希少な神社にかかわる事項
- 氏神・氏子とは何ですか?
上代、氏神は同じ祖先・同じ職業の人々(氏族)が信仰した神様でした。
時代が進み、氏族制度が壊れ、居住地が変わり、職業も変わり、昔のままの氏神を祀ることが出来なくなり、住んでいる土地の神(産土神ウブスナガミ)を氏神とするようになりました。
自身を生み育ててくれた地域・生活の基盤となっている地域の神様を氏神と呼ぶようになり、その地域に住み、その恵みに感謝する人々を氏子と呼ぶようになりました。- 御神符(オフダ)は何故毎年替えるのですか?薄い紙は?
形のあるものは年を経る毎に朽ちていきます。
しかし、神様の宿る御神符は清浄でなければなりません。
毎年お正月に御神符を替えるのは、神様の恵みと祖先の恩とに感謝し心を新たにするためです。
また、御神符にかかっている薄い紙は、御神符を保護するためのもので、包装紙のようなものです。本来は外します。- 数え年について教えて下さい
満年齢は、生まれた時がゼロ歳です。
数え年は、お母さんのお腹の中で命は脈々と育まれているという考え方から、誕生したときが一歳です。
そして、正月を迎える度に年齢を加えるのです。新しい年に幸せと安心を授けてくださる新しい魂の歳神様のお力で、人間をはじめ世の中の総てが生まれかわり歳を重ねます。- お供え物はどんな物でも良いのですか?
神様へのお供え物は食べ物(神饌シンセン)(古くは御饌・御食ミケ)、そして衣料・宝物・金銭(幣帛ヘイハク)、建造物(社殿・鳥居・灯篭)の三種類が基本です。
神様への感謝の誠を表すのがお供えです。神饌を例にすると基本は「米,酒,魚,海菜,野菜,果実,塩・水」です。
新鮮・旬・初物・地物が基本です。生のもの、火を通したものいずれもかまいません。
ただし、特殊神事を除き、獣の肉、辛いもの、匂いの強いものは避けて下さい。
お供え物は、神様への感謝の誠を形にしたということです。- 金銭をお供えする時の表書きは?
昔からの習慣で「初穂料ハツホリョウ」と書くのが一般的です。
初穂は稲の初穂ですが、現在では初物を神様に捧げるもの総てをさします。
その初穂のかわりに、初穂の分のお金を供えるからです。
神様に供えるということでは「玉串料」「神饌料」「幣帛料」などと書いてもよいでしょう。- おみくじの扱いはどのようにすれば良いのですか?
神社では古来、粥占、水占などいろいろな占いが行われ、おみくじ(御神籤)は、その一種です。おみくじには、総体的な運勢(大吉・吉…)と個々の運の判断(仕事運、金運…)が書いてあります。
大吉であっても浮かれずに精進するようにとか、凶でも用心して誠実にすれば神様のご加護がある、といった人生の大切な導きなのです。いたずらに喜んだり失望することではなく、その導きを守ることが大切です。このようなことから、持ち帰り時々読み返すことが良いようです。
おみくじの内容や運勢を神に託すという意味で境内の樹木に結ぶことが行われてきました。
樹木を傷めるという観点から最近は、結び所を設けている神社もあります。- 葬儀と神社とのかかわり方は?
近親者の場合、五十日間(忌中)神社・神棚の参拝をひかえます。
何よりも故人への慰霊を第一義とすること、近親者の死は深く大きな悲しみで神様にお参り出来る精神状態ではないことからです。
五十日を過ぎれば忌明けとなり元の普段の生活にもどります。
神様に忌中のご無沙汰をお侘びするお参りをします。喪中は一年間です。
この期間は年賀状を遠慮したり、中心となっての祝い事を延ばしたりします。
友人知人の葬儀に参列した日は、故人を失った深い悲しみで心は大きく乱れ平常ではありません。
心を鎮め平常心で参拝するため当日の神様への参拝は遠慮したいものです。- 神社と動物(神使)について教えて
『お稲荷さんの神様はキツネ?』と聞かれることがあります。
キツネが神様ではなく神様のお使いで、神使(シンシ、ツカハシメ)です。いろいろな神様に様々な動物がお使いとなっています。
例をあげますと、伊勢神宮の鶏、熊野大社の八咫烏(ヤタガラス…日本サッカー協会のシンボルマーク)、春日神社の鹿、八幡神社の鳩、天神さんの牛、白山さんの白馬など沢山の縁の深いお使いがいます。- 鈴(本坪鈴)について教えて
拝殿の前に吊り下げてある鈴を、本坪鈴(ホンツボスズ)といいます。参拝の合図お知らせではなく、鈴の清々しい音色を神様にお供えし、神様の御心をお慰めし、参拝する方も清らかな心になるためです。
- 御神酒、頂戴御神酒について教えて
お酒は、神饌の代表でもあり「神酒のあがらぬ神はなし」と例えられるくらい重要です。
そしてお祭りの最後に御神酒を戴く直会(ナホライ)をし、お祭りは完結します。
最近は、頂戴御神酒を遠慮される方がおられます。神社信仰にとって重要なポイントといえます。
御神酒は米を凝縮したものです。神様の御心・御恵みの籠もったものです。
御神酒の香りを戴くことも良いのではないでしょうか。- 鎮守の森(杜)について

昔から、鎮守の森(杜)いわれるとおり大木や樹林は神社にとって大切なものです。
神様の宿る依代(ヨリシロ)であったりもします。
外国の宗教では、建物を立派にし特別の空間を作ります。
神社は、建物だけではなく、その周囲の環境をも大切にします。神様のお住まいに相応しい清々しい雰囲気と邪気を寄せ付けないためにも木々を植え、森を形成し、大切にしてきたのです。
神様にとって、そして人間にとって緑深き森林は大切な存在であり、守り続けなければならないものなのです。- 禊祓(ミソギハラエ)について教えて
禊祓は、辛く苦しい体験を通して何かを超越しようとする「修行」や「荒行」とは違います。
罪(ツツミ)穢れ(キガレ)を除く『お祓い』なのです。
禊はお祓いの原形です。自らできるお祓いです。古事記にある『禊祓と神々の化生』を少なからず、再現し体験するものです。
正式な作法により禊祓を行うことにより、神代の神々の御心に触れることが出来るでしょう。
- 石川県内の神社は何社あるのですか?
現在、1862社の神社があります。これは神社本庁に包括されている神社の数です。
この他に、単立神社や宗教法人以外の神社もあります- 石川県内の神職数は何人ですか?
294名です。この内150名が宮司(本務)です。
神社数との違いでもわかるとおり多くの神社は神職が兼務しています。- 石川県で一番高い所にある神社は?
白山山頂(標高2702メートル)の御前峰に御鎮座の白山比咩神社の白山奥宮です。
山岳信仰は、全国各地に見られるますが、白山は、富士山・立山とともに三大霊峰に数えられ、日本の山岳信仰の代表として古くから多くの人々の信仰を集めています。- 石川県で一番北にある神社は?
現能登半島の北端から約48kmにある平らな島、舳倉島。輪島市の舳倉島は、神々の島とも呼ばれ、歩いて一周して一時間程度の小さな島に、8つの神社があります。
神社の他に小さな祠や石造物が至るところに見られます。大宮「奥津比咩神社」は総鎮守と位置付けられています。
ちなみに、一番東は、珠洲市三崎町の八幡神社。西は、加賀市塩屋町の八幡社。南は白山奥宮です。- 能登のキリコ祭りについて教えて下さい

7月上旬から9月中旬まで能登の各地(代表的な祭 26)で繰り広げられる他県では見られない、独特の雰囲気を持った伝統行事。
「キリコ」とよばれる巨大な御神燈を担ぎ、お御輿のお供をして夜を徹して練り歩きます。
大きさは、高さ12m超、重さ2t、百人以上の担ぎ手を要する巨大な物もあります。
最近は、街の形態から4~5m程のキリコが主流です。キリコ(切籠))とは、切子灯籠(きりことうろう)の略称。奥能登に発祥し、中能登に伝搬したもので、中能登では、ホートー(奉燈)オアカシ(御明かし)と称するところもあます。- 「あえのこと」について教えて下さい
奥能登一円の農家で毎年12月5日に行われる田の神様を自宅にお招きし、その年の一年の収穫に感謝する「田の神様まつり」。
各家々で内容は異なるようですが、代表的なものは、家の奥座敷に種もみの俵を一対据えて神座を設け、二俣の大根をのせます。
田の神様は夫婦神で目が不自由。主人は田圃に出向き丁寧にお導きし、入浴していただいた後、座敷に案内します。
手作りの栗の木の箸をのせた御前に、真心をこめて作ったご馳走でおもてなしします。
田の神様は、その家でゆっくり年越しされ、2月9日に「田の神送り」(同内容のもてなし)で田圃に帰られます。国指定重要無形民族文化財です。
また、ユネスコ無形文化遺産(世界無形遺産)に登録されました。- 全国的に珍しい御祭神をお祀りしている神社はありますか?
金沢市二日市町に日本唯一の「香辛料」の神様、生姜の古名「薑(はじかみ)」を名乗る波自加彌神社があります。
波自加味大神は、歯で噛んで辛いもの(しょうが・山椒・わさび)の祖神様です。
毎年6月15日に行われる「しょうが祭」には、全国から生姜栽培加工業者や食品加工業者などの参詣があります。- 石川県には源義経ゆかりの神社が多いと聞きますが?
兄の源頼朝に謀反を疑われ、追われる義経が奥州平泉へと落ちのびる途中、石川県内各地に伝説を残しています。
能「安宅」、歌舞伎「勧進帳」でお馴染みの小松市の安宅住吉神社。
安宅の関を無事通過することを祈願し義経が植えた「牛若松」がある小松市の兎橋神社。
白山に武運を祈願し夜通し神楽を奏し義経が腰掛けたとされる石が残る白山市の金剱宮。
弁慶が冨樫氏の館を訪ね時、軽々と投げた大岩がある野々市市の布市神社。
冨樫氏の館を訪ねた弁慶を待ち義経一行が一夜を明かした「一夜泊まりの宮」と呼ばれる金沢市の大野湊神社。
冨樫氏が義経一行に追いつき、義経の勇気と弁慶の知恵に感服し酒を差し入れ宴を開いた金沢市鳴和の鹿島神社。
義経一行が運悪く大嵐に遭い三崎権現で航海安全を祈願した。
海が穏やかになったことに感謝し、義経は「蝉折の笛」を弁慶は「短刀」を奉納し今も宝物として拝観できます。
また、境内には「義経駒の爪石」が残る珠洲市の須須神社等があります。- 全国的に珍しい神事を教えて下さい。
加賀市菅生石部神社の「竹割まつり」の俗称を持つ御願神事。
毎年二月十日に斎行される例祭で、祭典の後、青壮年数十人が白衣白短袴姿で境内に突入し、二メートル余の青竹を激しく地面に打ちたたく姿は壮絶をきわめます。
続いて拝殿から大蛇に擬した長さ二十メートル太さ三十センチもの長縄を引き回し、大聖寺川に投げ入れる勇壮な神事があります。
能登町宇出津の酒垂神社、八坂神社の「あばれ祭」は悪病平癒祈願を盛大に行ったところ、祭神が神霊と化した青蜂が悪疫病者を救いました。
喜んだ人々がキリコを担いで神社に感謝したのが始まりのこの神事は、四十数本のキリコと二基の御輿が町を練り歩きます。
この間、御輿は海や川、火の中に投げ込まれ暴れれば暴れる程、壊れる程神様が喜ばれるといわれる勇壮な海の神事です。